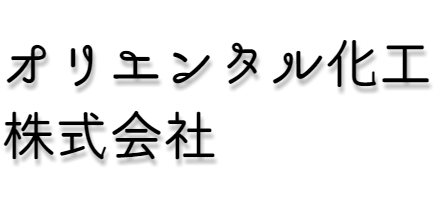第2回 大石神社・岩屋寺──「忠臣蔵」ゆかりの地
山科についてご紹介していく「山科めぐり」。2回目の今回は、時代劇の「忠臣蔵」で有名な大石神社と岩屋寺を紹介します。
徳川綱吉の時代、江戸城で播磨赤穂藩主の浅野長矩(ながのり)が遺恨のあった吉良上野介(きらこうずけのすけ)に切りかかりました。当時は喧嘩両成だったのに、将軍綱吉は浅野に切腹を命じ、赤穂藩の取り潰しを決めたいっぽうで、吉良にはお咎めなしでした。これに不満を抱いた浅野の家臣たち(赤穂浪士)47人が主君の名誉を回復するため上野介を殺害し、仇討ちを成し遂げた事件をもとにしたのが「忠臣蔵」です。
大石神社は、この「忠臣蔵」の物語の主人公である大石内蔵助(おおいしくらのすけ)を祀っている神社です。
大石内蔵助が「忠臣蔵」の作戦を練った地
「忠臣蔵」の広がり
内蔵助ら赤穂浪士たちによる討ち入りは、江戸の社会に衝撃をもたらしました。 武士の人々には、士農工商の身分制度の上に安逸をむさぼっていることへの危機感を与えました。いっぽう、町人の人々からは「義挙」(正義のための行動)として評価され、幕府の一方的な処置への批判を吹き飛ばすような快挙として喝采を浴びました。 その影響は、事件落着後すぐから歌舞伎や浄瑠璃の格好の題材になったことからもうかがえます。この事件を題材にしたなかでも最も有名なのが、1748年から演じられるようになった浄瑠璃『仮名手本忠臣蔵』です。この9段目において、内蔵助の「山科閑居」が初めて独立した位置づけを与えられるようになりました(※3)。この作品は浄瑠璃三代名作の一つとされ、内蔵助と山科の関係が広まるのに大きく貢献しました。 |
京都の人々による創建
大石神社が建てられてのは昭和に入ってから、1930年代のことです。 発端は四十七士の義挙を顕彰する神社を建てようとする浪曲師・吉田奈良丸の提唱でした。この提唱に京都府・京都市が賛同し、府知事を会長とする大石神社建設会によって大石神社が創建されました(※3)。 明治期から近代にかけての神社の区分では、神社は国家が管理する国幣社(こくへいしゃ)と、氏子や崇敬者によって維持される府県社や郷社に分けられます。大石神社は京都府が主導して建てられた由縁から府社にあたり、今でも大石神社の入口には「府社」と書かれています。 とくに府県社には人臣を祀る神社が多く(※4)、人格への崇敬と宗教的な崇拝が結びつけられていきました。大石神社の創立も、こうした流れに与するものとしてとらえることができます。 |
「大願成就」のご利益
冷静に作戦を練り仇討ちという大挙を果たした四十七士を祀っていることから、大石神社は「大願成就」の神徳でたたえられています。 ご神木は「大石桜」とされています。これは、ご鎮座のときに大石内蔵助の隠棲の地に生育していた「しだれ桜」を整備の終えた境内に定植させたものです。 今も境内にはたくさんの桜があり、春にはお花見客が絶えません。
|
注・写真は2020年4月7日に非常事態宣言が出されるより以前のもので、お昼休みに撮られております。
2020年4月現在のこの情勢では不要不急の外出はお控えください。
※1)鏡山次郎.(2017).『京都山科史跡楽訪』.山科・史跡楽訪の会.
※2)ふるさとの会歴史街道・史跡巡り部会(著),鏡山次郎(編).(2018).『山科辞典』.ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会.
※3)後藤靖,田端泰子.(1992).『洛東探訪―山科の歴史と文化 』.淡交社.
※4)森岡清美.(2003).「明治維新期における藩祖を祀る神社の創建―旧藩主家の霊屋から神社へ,地域の鎮守へ―」.『淑徳大学社会学部研究紀要』,(37),125-148.
大石神社Webサイト:http://www.ooishijinja.com/